「どうしてこんなに落ち着きがないんだろう?」「言ってもすぐ忘れてしまう…」「体育が苦手で自信をなくしてる…」
そんな子どもたちの姿に、戸惑いや心配を感じたことはありませんか?
実は、子どもの「できる・できない」には、脳の発達の順序やスピードが大きく関わっています。
脳は、生まれてから思春期にかけて段階的に育っていくため、まだうまく働かない機能があって当然。
この記事では、理学療法士の視点から、子どもの脳の発達の仕組みや、それに応じた「困りごと」とのつながり、そしてサポートに役立つ運動や遊びの工夫についてお伝えします。
学校や家庭での支援に、ぜひお役立てください。
脳は「下から上へ」「後ろから前へ」育っていく
人の脳は、生まれる前から発達を始めますが、成長の中心は乳幼児期から学童期にかけて。
しかも、いきなり全部が一気に育つわけではなく、順序があります。
まず育つのは「脳幹」という、呼吸や心拍など生きるために大事な部分。
次に「感情」や「欲求」をコントロールする部分、
最後に「考える・覚える・我慢する」などの高い働きをする「大脳新皮質」が育ちます。
さらに、脳の場所としては、後ろ(視覚や感覚のエリア)から前(前頭葉=おでこの内側)へと発達していきます。
つまり、まず「感じる・動く」ができるようになり、だんだん「考える・計画する」力が伸びていく、という流れです。
前頭葉の中でも特に大事な「前頭前野(ぜんとうぜんや)」は、大人のように働くまでに20歳近くまでかかると言われています。
年齢による発達の特徴と「困りごと」との関係
乳幼児期(0~3歳)
感覚や運動の力がぐんと伸びる時期。見たり触ったり動いたり…まさに「体で世界を知る」毎日です。
この時期に大切なのは、五感への刺激とたっぷりの運動。
たとえば、ハイハイや転がる、手で物をつかむ、口でなめる…こうした経験が、脳のネットワークづくりの土台になります。
幼児期~学童期(4~12歳)
言葉・思考・社会性が一気に伸びる時期。学びの力も育っていきますが、まだ「衝動のコントロール」や「注意を続ける力」は発展途上。
「じっと座っていられない」「何回言っても忘れる」「感情の起伏が激しい」などは、前頭前野がまだ育ちきっていないサインかもしれません。
また、感覚の過敏さや鈍さも目立ってくる頃。
たとえば「服のタグが気になって集中できない」「大きな音でパニックになる」などの行動も、感覚処理のバランスによるものです。
思春期~青年期(13歳~)
体も心も大きく変わる時期。見た目は大人に近づいても、脳はまだ発達中です。特に「感情」と「理性」のバランスを取るのが難しい時期。
反抗的に見える行動の裏にも、「言葉にできない不安」や「整理しきれない感情」が隠れていることがあります。
運動と感覚刺激が脳を育てる
子どもの脳は、経験によってどんどん変化していきます。
これを「神経の可塑性(かそせい)」といいます。特に、運動や感覚の体験は、脳のつながりを強くしてくれる大事な栄養なんです。
たとえば…
- ブランコやぐるぐる回る遊具 → バランス感覚や空間認識を育てます
- 粘土や砂遊び → 手の感覚や集中力を高めます
- 跳び箱や鬼ごっこ → 全身を使って自分の体をコントロールする力を鍛えます
こうした遊びを通して、姿勢を保つ力、集中力、感情の安定などが自然と育っていくのです。
学校や家庭で見られる「困り感」は脳の発達段階とつながっている
「姿勢が崩れる」「すぐに立ち歩く」「感情が爆発する」…こうした行動が、わがままや甘えではなく、発達途中の脳の特徴だとしたらどうでしょうか?
たとえば…
- 集中が続かない → 前頭葉のネットワークがまだ未熟
- 刺激に敏感すぎる → 感覚処理が未発達
- 協調運動が苦手 → 前庭や固有感覚の統合が不十分
このように、表に見える行動の裏には、脳や感覚の働きが関係していることが多いのです。だからこそ、叱るのではなく、どう支えるかが大切になります。
家庭や学校でできる「脳を育てる遊び・運動」
以下は、日常で取り入れやすく、脳の発達にも効果的な活動の例です。
- バランスあそび:片足立ち、クッションの上を歩く、バランスボールに座るなど
- 回る・揺れるあそび:ブランコ、回転いす、トランポリンなど(やりすぎには注意)
- 触覚あそび:粘土、砂、スライム、タオルで体を包むなど
- 音とリズム:音楽に合わせて体を動かす、手拍子、リズム遊びなど
- 「止まる・動く」のゲーム:だるまさんがころんだ、赤信号ゲームなど
これらの遊びを無理なく、楽しく取り入れていくことが、子どもの脳と心をじっくり育てていく近道になります。
理学療法士として伝えたいこと
理学療法士は、体の使い方や感覚の働き、そしてそれに基づく行動の背景を観察・分析し、「なぜその行動が出るのか?」を一緒に考える専門職です。
単に動きを見るだけでなく、姿勢や感覚のバランス、脳の発達段階など、子どもの中にある理由を探りながら、適切な支援の形を提案しています。
もし、「この子、何か困っているかも」と思ったとき、行動の表面だけを見て判断せず、「どんな発達の途中なんだろう?」と視点を変えてみてください。きっとサポートのヒントが見えてきます。
まとめ:脳の発達を知ることは、子どもを理解することにつながる
子どもは「今できること」「まだできないこと」を持ちながら育っています。
それは欠点ではなく、「発達の途中」だからこそ起こる自然な姿です。
脳の育つ順番やタイミングを知ることで、「困り感」の見方が変わり、支援の手立ても広がります。
家庭や学校、そして専門家と一緒に、「その子らしい育ち方」を支えていけたらと願っています。
もっと詳しい脳の発達に関して興味がある方はこちらを👇
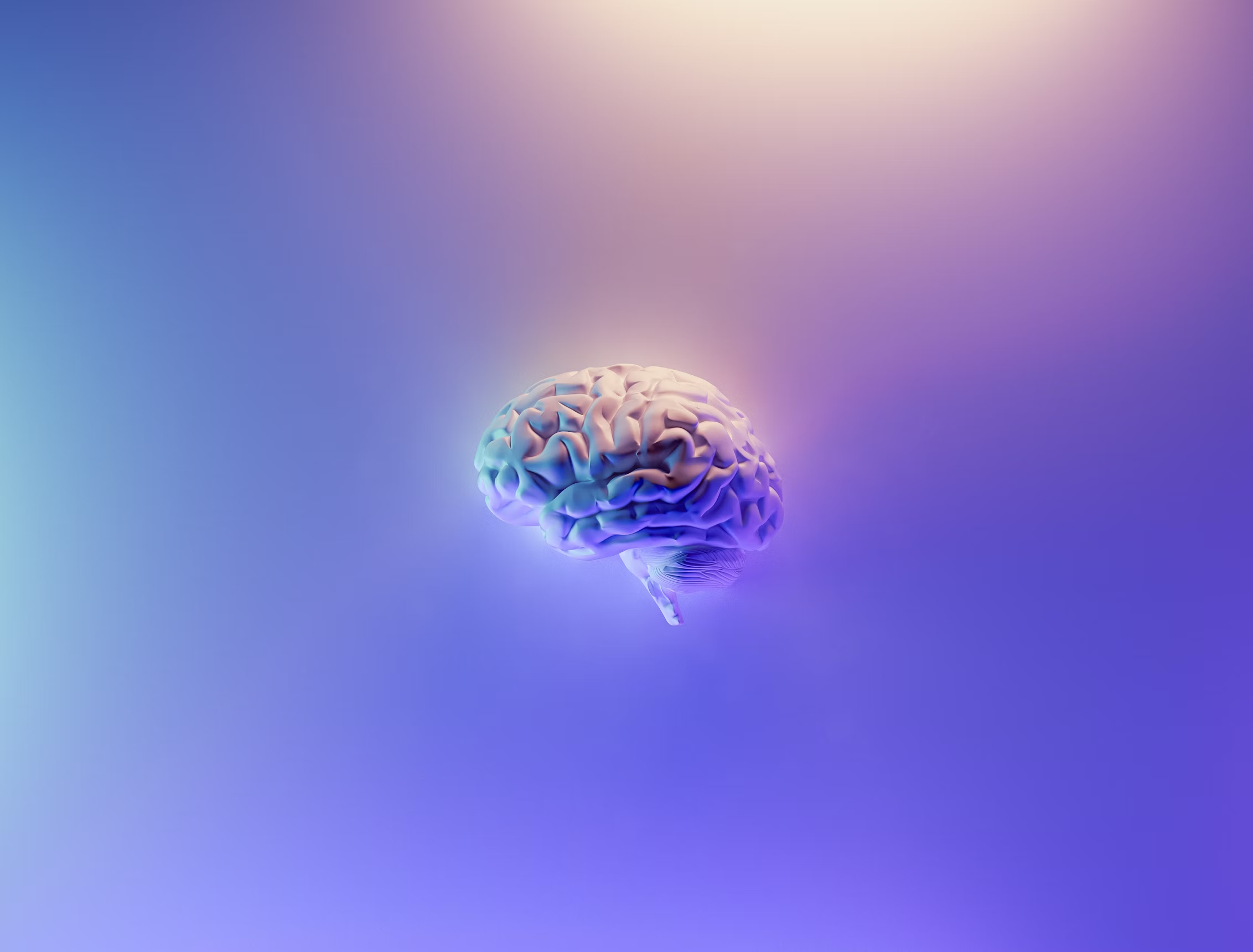
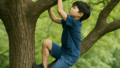

コメント