「子どもがじっとしていられない」「座っている時間が続かない」――そんな様子に不安を感じる保護者は多いものです。
これは必ずしも「落ち着きがない」ことを意味するのではなく、発達段階で自然にみられる特徴であったり、感覚刺激や身体の動きを求めることによるものです。
理学療法士として強調したいのは、子どもの「動き」には意味があり、工夫次第で支援に変えられるということ。
この記事では、科学的な知見と臨床に基づくアイディアを交えながら、室内でできる支援方法を紹介します。
なぜ子どもはじっとしていられないのか?
1. 発達に伴うエネルギー需要
子どもは成人よりも基礎代謝が高く、筋肉や脳の成長に多くのエネルギーを使います。
そのため、自然に「体を動かしたい」という欲求が強く表れやすいのです。
2. 感覚統合の発達段階
脳は、動きや感覚刺激を通じて発達します。特に前庭感覚(平衡感覚)や固有感覚(筋・関節の位置感覚)は、体を動かすことで磨かれていきます。
→ 座ってじっとするよりも「動いている方が落ち着く」子がいるのは、この感覚統合のプロセスと関係しています。
3. 注意の持続時間の発達
- 7歳から85歳までを対象にした研究で、子どもの注意持続時間は大人よりも明らかに短いとされ、特に「ゾーンに入った」集中状態を維持できる時間が限られていることが示されました。
- 10~11歳児を対象とした研究では、注意の持続は「感情の安定性」「外向性」「学習への動機」などの内的要因に加え、母親との関係や日常生活のリズム(例:睡眠や家庭環境)などの社会的要因によっても強く影響を受けるとされています。
- 7~12歳を対象に7つの注意機能(持続・選択・分割など)を測定したところ、9歳以降に「知覚的注意」と「実行的注意」の2つの要素が分化し始め、大人の注意機能に近づくという結果が得られました。
室内でできる科学的に有効な支援アイディア
1. 「動ける時間」を組み込む
- 学習や活動の前に 3〜5分の運動タイム(ジャンプ、ストレッチ、体幹運動)を設ける
- 集中と運動を交互に行う「ポモドーロ的リズム」を取り入れる
軽度の運動は前頭前野の血流を増やし、注意・実行機能を高めることが示されています
2. 感覚を満たす遊び
- クッションの上でバランス遊び
- タオルボールを的に投げる
- 室内サーキット(椅子をくぐる、布団の上を転がるなど)
これらは 前庭感覚・固有感覚を統合 する活動で、落ち着きや姿勢制御を育む効果があります。
3. 「手を動かせる」工夫
- 学習時にストレスボールや粘土を触らせる
- ペン回しや小さな工作を許可する
手を動かす活動は感覚入力を増やし、脳の覚醒レベルを適度に高めることが知られています
4. 姿勢を許容できる環境づくり
- バランスボールやクッションに座らせて「小さな揺れ」を許す
- 立って作業できる机を用意する
姿勢を変えられる環境は「動きを抑制するよりも集中を維持しやすい」ことが報告されています
5. ミニ休憩の導入
- 10〜15分集中 → 2分間動く
- 「水を飲みに行く」「窓を開けに行く」といった小さな動きでも効果あり
短い休憩は集中力の回復に有効であり、特に小児では学習効率を高めることがわかっています
支援のポイント
- 「じっとさせる」より「動きを調整できる環境づくり」 が大切
- 動くことで得られる感覚は、体幹や姿勢の安定、集中力の基盤 を育てる
- 支援者・保護者が「動きながら集中する」子の特性を理解することが、安心と成長につながる
まとめ
子どもがじっとしていられない背景には、
- 発達に伴う自然なエネルギー需要
- 感覚統合の発達プロセス
- 注意持続時間の短さ
が関わっています。
そのため、「無理に止める」のではなく「動きを支援に変える」 ことが重要です。
理学療法士として強調したいのは、動きは体の成長と心の落ち着きにつながる ということ。
家庭でも取り入れられる小さな工夫を積み重ねることで、子どもが「安心して、集中できる」室内環境を整えていけるでしょう。


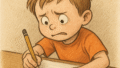
コメント