「最近、子どもが外で遊ぶ時間が減っている」「ゲームや動画の時間が多くて、体を動かす機会が少ない」
そんな現状に心配を感じていませんか?
実は、“遊び”こそが子どもの発達を支える最も自然で、最も科学的なトレーニングです。
運動・考える力・心の安定――この3つは遊びの中で同時に育ちます。
本記事では、科学的な知見を踏まえつつ、保護者・支援者が家庭・園で実践しやすい形でお伝えします。
1. はじめに:なぜ“遊び”なのか
「遊び=子どもの余暇/気ままな活動」だけではなく、発達を支える重要な“場”です。
発達心理学・教育学・神経科学とも関連付けられ、「遊びは子どもにとっての“仕事”(=成長のための活動)」という考えが広まっています。
例えば、既存のレビューでは、遊びを通じた体験が学習・発達に関連しているという証拠が多数示されています¹⁾。
理学療法士としても、「遊び」の中に含まれる 体を使う動き(運動)、試行錯誤して考える(認知)、他者と関わる・気持ちを経験する(情緒・社会性) が、子どもの総合的な発達を支えている点に注目しています。
2. 運動発達:体を使った遊びで作る“動きの基盤”
なぜ運動が重要か
体を動かす遊び(走る・跳ぶ・投げる・バランスを取るなど)には、次のような発達的意義があります。
- 筋力・持久力・バランス感覚・空間認知(どこに体があるかを感じる)などの運動機能が育つ
- 体幹や手足の動きを分離して使えるようになることで、座る・書く・歩くといった日常動作や学習姿勢にもつながる
- 身体活動は認知機能・情緒とも結びついており、例えば「動ける」「動いた」経験が自己効力感(「自分にもできた」という感覚)を育てる
運動+認知の統合例:研究の知見
最近のメタアナリシスでは、「認知的に関わる運動(cognitively engaging physical activity)」つまり、単に動くだけではなく考えながら動く遊び・活動が、子どもの実行機能(executive functions:抑制・更新・切り替えなど)を改善する効果があることが明らかになっています²⁾。
例えば35分以上のセッションで(子ども4〜12歳対象)全体的な実行機能スコアが有意に改善されたというデータがあります²⁾。
→ 理学療法的には「ただ走らせる」のではなく、「目的をもって動く」「考えながら動く」「ルールを付けながら動く」遊びが有効ということが分かります。
家庭で取り入れられるヒント
- 床にテープやチョークで「線」や「丸」「三角」を描いて、線の上をバランス歩き+途中で「○をタッチして戻る」等のルールを付ける
- 風船を使って「風船を上げたまま〇秒キープ+そのあと反対方向に移動」という遊び。風船が落ちないように動きを予測・調整することで、運動+認知が刺激されます
- 公園で「木の根っこをまたぐ」「段差を越える」など、段差・不安定な足場を活かした遊び。バランス→反射→体幹の調整が育ちます
3. 認知(思考・試行錯誤・計画)を育む遊びの構造
遊びが認知を育てるメカニズム
子どもが遊びながら「どうすればうまくできるかな?」「次はどうしようかな?」と考えるプロセスそのものが、認知機能を鍛えています。特に以下のような力が遊びを通じて育ちます。
- 問題解決力・創造性:積み木を倒さずに積む、隠れ家を作る、など
- 計画性・実行・評価:遊びながら試して修正を繰り返す記憶・柔軟性
- 空間認識・数・リズム・タイミング:ケンケンパ、跳び箱、ボール遊びなど
ガイド付き遊び(guided play)の効果
研究でも、完全に自由な遊びと、直接的な指導の中間に位置する「大人がサポート・誘導を入れた遊び」が、幼児期において学習効果を高めるというメタ分析があります³⁾。
→ 保護者・支援者としては、「遊びを見守るだけ」ではなく、子どもの遊びに軽くヒントを出したり一緒に試したりすることで、認知の育ちをさらに促せるということです。
家庭で取り入れられるヒント
- 積み木遊びで「今日はこの形で塔を作ってみよう」「倒れないようにどう積めばいいかな?」と問いかける
- 「〇から△に移動→△から□に移動」という順序を子どもと決めて、動いてみる(例:フローリングの上にテープで三角・四角を描いて)
- ごっこ遊びで「次どうする?」「役割を交代しようか?」と子どもに選択肢を与える。選択を通じて計画・決定・実行を体験できます
4. 情緒・社会性:遊びだからこそ育つ“こころの力”
情緒・社会性が育つ遊びの特性
他者と関わったり、自分の気持ちを表現したり、失敗や成功を経験したり――遊びはこうした「心の動き・人とのやり取り」を豊富に含みます。これにより、
- 自己肯定感・意欲が育つ(「できた」「楽しい」が積み重なる)
- 共感・他者理解・順番・ルールを守る力など社会性が育つ
- 情緒のコントロール(興奮・我慢・悔しさ)を安全な場で経験する
「ごっこ遊び/象徴遊び(pretend play)」の研究知見
3〜8歳を対象としたメタ分析では、ごっこ遊び(=「~の役を演じる・想像して遊ぶ」形式)と社会的能力(social competence)には正の関係があるという結果が出ています⁴⁾。
ただし、「ごっこ遊びが社会的能力を必ず育てる」ことを証明する因果関係まではまだ明確ではない、という注意点も示されています。
→ つまり、ごっこ遊びが“関係をつくりやすい場”を提供する可能性が高いということです。
遊び機会が少ない子ども・特別な支援が必要な子どもへの示唆
遊び量が少ない・遊び参加が制限されている子ども(例:慢性的な健康条件・発達特性を持つ子ども)は、遊びを通じた発達機会が少ないという研究もあります⁵⁾。
支援現場では、動きや感覚の制限がある子どもに対して“遊びをどう設計し支援するか”が重要になってきます。
家庭で取り入れられるヒント
- ぬいぐるみ・お人形・紙皿や段ボールで「お店屋さんごっこ」「秘密基地ごっこ」を一緒にやってみる。子ども自身に役割を“選ばせる”ことで主体性が育ちます
- 順番を持つ遊び(例えばボールを転がして相手が取る、「どうぞ/ありがとう」で返す)で社会的なやり取りを体験する
- “負ける”“失敗する”経験があっても「いいね、次どうする?」と支援者が受け止めることで、情緒面の成長を促す
5. 三者(運動・認知・情緒)が統合される遊びの良さ
ここまで別々に見てきましたが、実は“遊び”では運動・認知・情緒がほぼ同時に働くことが多いのが特徴です。
理学療法士として特に注目したいこの統合性について触れます。
- 例えば「鬼ごっこ」:走る/止まる(運動)+どこに逃げるか考える(認知)+友だちと一緒に遊ぶ・ルールを守る・興奮をコントロールする(情緒・社会性)
- 「積み木で塔を作って友だちと順番で積む」:手指や体幹の使い方(運動)+どこに積む・どうすれば崩れないかを計画(認知)+友だちとのやりとり・相手の意見を聞く(情緒・社会性)
- また、先述の「認知的に関わる運動」が実行機能を改善するという研究も、まさにこの“運動+認知”の統合を指しています。
このように「遊び」は、分野をまたいで発達を支えてくれる非常に効率的な活動なのです。
6. 理学療法士視点で押さえておきたいポイント(支援・介入編)
保護者・教員・支援者として “遊び” を意図的に支援・促す際に、理学療法的な視点から特に重要だと考えるポイントをお伝えします。
ポイント① 子どもの「動きの質」を観察する
- 体幹が安定していない、すぐ膝が曲がる/バランスが取れない、歩き方がぎこちない場合、遊びの中での「動きの質」に注目。遊びを通じた体幹・バランス強化が有効
- 例えば、遊びの中で「始めと終わりをきちんと止める」「片足立ちでポーズをキープする」等のミニチャレンジを入れてみる
ポイント② 遊びに「少しのサポート・誘導」を加える
- 前述の考え方を取り入れ、完全に自由放任ではなく、問いかけ・ヒント・振り返りを加えることで、認知・社会性の発達をさらに促せます。
- 例:「どうやったら積み木が倒れないかな?」→「少し幅を広く積んでみようか?」「今の高さで止めるならどうしたら?」と促す
- また、子どもの遊び中に「いいね、次どうする?」「それ面白いね、他には?」と関わることで、思考の深化が期待できます。
ポイント③ 情緒・社会性を育てる遊び環境を整える
- 友だち・兄弟・保護者との関わりがある遊びを増やす。順番・やり取り・ルールのある遊びが特に有効
- 感情が揺れ動く(悔しさ・喜び・驚き)状況を安全に体験できるよう「今日だけルールを少し変えてみよう」「こういう風にやってみよう」と遊びを工夫
- 遊びがうまくいかなかったときに「どうしたら次はうまくいくかな?」と子どもと一緒に振り返ることで、メタ認知的な力(自分の遊びを振り返る力)も育ちます。
ポイント④ 発達に偏りがある子どもへの配慮
- 動き・遊びの経験が少ない子ども(例:感覚過敏・運動苦手・発達特性あり)は、遊び機会そのものが少ない傾向があります。例えば、メタ分析では「遊び時間・遊び質ともに少ない」という報告があります⁶⁾。
- こうした場合、「難しさを軽減した遊び」「成功体験を重ねられる構造」「遊びの環境調整(安全・安心・選びやすさ)」がカギとなります。
- 例えば、足場の不安定な公園遊びが難しいときには、室内でクッションやマットを使った「安全に少し不安定な足場」を作る。動きを少しずつ広げていく支援を行う。
7. 保護者・教員が今日からできる“遊び活用チェックリスト”
以下のチェックリストを参考に、「遊びを支える環境づくり」「遊びに少しだけ工夫を加える」習慣化してみてください。
- 子どもが自由に動ける時間・場所を1日1回は設けている
- 動きを使った遊び(走る・ジャンプ・バランス)を“2分でも”意図的に取り入れている
- 遊び中に「どうしたらうまくいく?」と問いかけたことがある
- ごっこ遊び・役割遊びを週1回以上取り入れている
- 友だち・兄弟・保護者と関わる遊び(順番・ルールあり)を意識している
- 遊びに失敗・転倒・悔しさがあったとき、「どうだった?次どうする?」と一緒に振り返った
- 遊びが苦手・動きに不安定さがある子どもには、安全にチャレンジできる遊び環境を用意している
8. “遊び”が生み出す長期的な影響と理学療法的視点の意義
研究は、「質の高い幼児期の遊び・体験」がその後の学び・社会性・情緒の発達に影響を与えていることを示唆しています。
例えば、幼児教育プログラムのメタ分析では、早期教育プログラム(遊びや体験を含む)が子どもの認知・社会・情緒に有意な改善をもたらしたという報告があります⁷⁾。
幼少期に体・動き・遊びを通じて“発達の基盤(身体・感覚・運動)”がしっかり作られていると、後々の学習・日常生活動作・健康維持にも好影響を及ぼすということです。
特に、発達が気になる子ども・感覚運動面に不安がある子どもにとって、遊びを通じたアプローチは「楽しみながら発達を支える」非常に有効な手段です。保護者・支援者・理学療法士・教員が連携して、遊びを支援する環境を整えることが望まれます。
9. まとめ:遊びは“成長のための活動”であり、理学療法的支援の場でもある
遊びは、ただ「自由に遊ばせておけば大丈夫」というだけではなく、運動・認知・情緒という三つの要素を同時に育てる“統合的な成長の場”です。
- 観察ポイント:子どもの動き・遊び中の関わり・感情の動き
- 支援ポイント:遊びに少しサポートを入れ、成功体験を設計し、他者との関わりを促す
- 環境設計:安全・適度なチャレンジ・子どもの主体性を尊重する
- 長期視点:幼児期の遊び経験がその後の発達・学び・健康に影響を与える可能性がある
保護者・教員・支援者が「遊びを大切にする」姿勢を共有し、日々の中で“遊びの質”を意識することが、子どもの発達を大きくサポートします。
すこっぴーラボでは、理学療法士の視点をもとに、子どもの発達や成長に関する情報発信を行っております。
お子さんの発達や遊びの工夫についての 無料相談 も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。


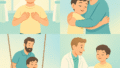
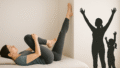
コメント