夏休みが終わり、いよいよ新学期のスタート。
長い休みの間に生活リズムが変わり、学校生活に戻るときに「体がついていかない」と感じる子どもは少なくありません。
- 朝起きられない
- 集中が続かない
- 姿勢が崩れる
- 「学校に行きたくない」と言い出す
こうした不調の背景には、生活リズムの乱れだけでなく、体の感覚(特に前庭感覚) が休み中に十分に使われず、調整力が落ちてしまっていることも関係しています。
今回は、理学療法士の視点から、夏休み明けに起こりやすい不調とその対策について詳しく解説します。
夏休み明けに見られる子どもの不調
1. 生活リズムの乱れによる不調
- 睡眠時間が不規則になり、朝起きられない
- 昼間に眠気が強く、集中力が続かない
- 食欲が安定せず、食べ過ぎや食欲不振が見られる
👉 「生活リズムを学校モードに戻す」ことが最初の課題になります。
2. 前庭感覚の低下による不調
前庭感覚とは、耳の奥(内耳)にある器官が、体の傾きや動きを感知して姿勢やバランスを保つために働く仕組みです。
長期休み中は、外で遊ぶ機会が減り、体を大きく動かす経験が少なくなりがちです。
その結果、以下のようなサインが見られることがあります。
- 授業中に姿勢が崩れやすい
- 机にうつ伏せになったり、体を揺すったりする
- 集中が続かず、気持ちが不安定になりやすい
- 運動するとすぐ疲れる
👉 前庭感覚は「姿勢の安定」だけでなく「情緒の安定」にも関わるため、不調が心身の両面に出やすいのです。
3. 情緒面での不安定さ
- 新しいクラスや先生に慣れるまで時間がかかる
- 「友達とうまくやれるかな」という不安が出やすい
- 学校に行き渋る、体の不調を訴える
休み明けは「心のエネルギー消費」が大きく、特に繊細なお子さんほど不安定になりやすい時期です。
夏休み明けにできる生活リズム調整の工夫
1. 睡眠リズムを整える
- 就寝・起床時間を一定にする
- 朝はカーテンを開けて太陽光を浴びる
- 寝る前のスマホやゲームは控え、リラックス時間を確保する
👉 光の刺激と体の活動リズムが合うと、自然と眠りやすく、朝も起きやすくなります。
2. 食事リズムを意識する
- 朝ごはんは必ず摂り、体のエンジンをかける
- タンパク質(卵・魚・豆腐など)を取り入れると集中力も安定
- 水分不足にならないよう、こまめに水を飲む
3. 運動で前庭感覚を刺激する
前庭感覚を育てるには、体を大きく動かす遊びがとても効果的です。
おすすめの遊び
- ブランコやすべり台(揺れる・回る動き)
- 鉄棒のぶら下がり(逆さまの姿勢を体験)
- 鬼ごっこや縄跳び(全身を使った動き)
- 親子で手をつないで回る「ぐるぐる回転」
👉 毎日10〜15分でも「体を揺らす・回す・ぶら下がる」動きを取り入れると、姿勢の安定や集中力アップにつながります。
4. 親子の安心感を大切にする
- 「夏休み終わっちゃったね。寂しいけど頑張ろうね」と気持ちを共感する
- 「今日はどんなことがあった?」ではなく「給食おいしかった?」など答えやすい質問から始める
- 行き渋りがあるときは「まずは学校の門まで行ってみよう」と小さな目標を立てる
👉 子どもは「気持ちを言葉にして安心する」経験を積むことで、徐々に心の安定を取り戻します。
まとめ
夏休み明けは、子どもにとって「生活のリズムを取り戻す大切な時期」。
特に前庭感覚の刺激が不足すると、姿勢や集中力、情緒の安定にも影響します。
- 睡眠・食事のリズムを整える
- 毎日少しでも体を大きく動かす
- 親子の安心感を大切にする
この3つを意識するだけで、不調の多くは和らいでいきます。
すこっぴーラボからのご案内
すこっぴーラボでは、お子さん一人ひとりの特性や動きの特徴を丁寧に見きわめ、その子に合ったサポート方法をわかりやすくご提案しています。
無料相談も受け付けていますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
理学療法士が専門的な視点でお子さんの動きや特徴を分析し、保護者の方や先生と一緒に最適なサポート方法を考えます。
「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします。


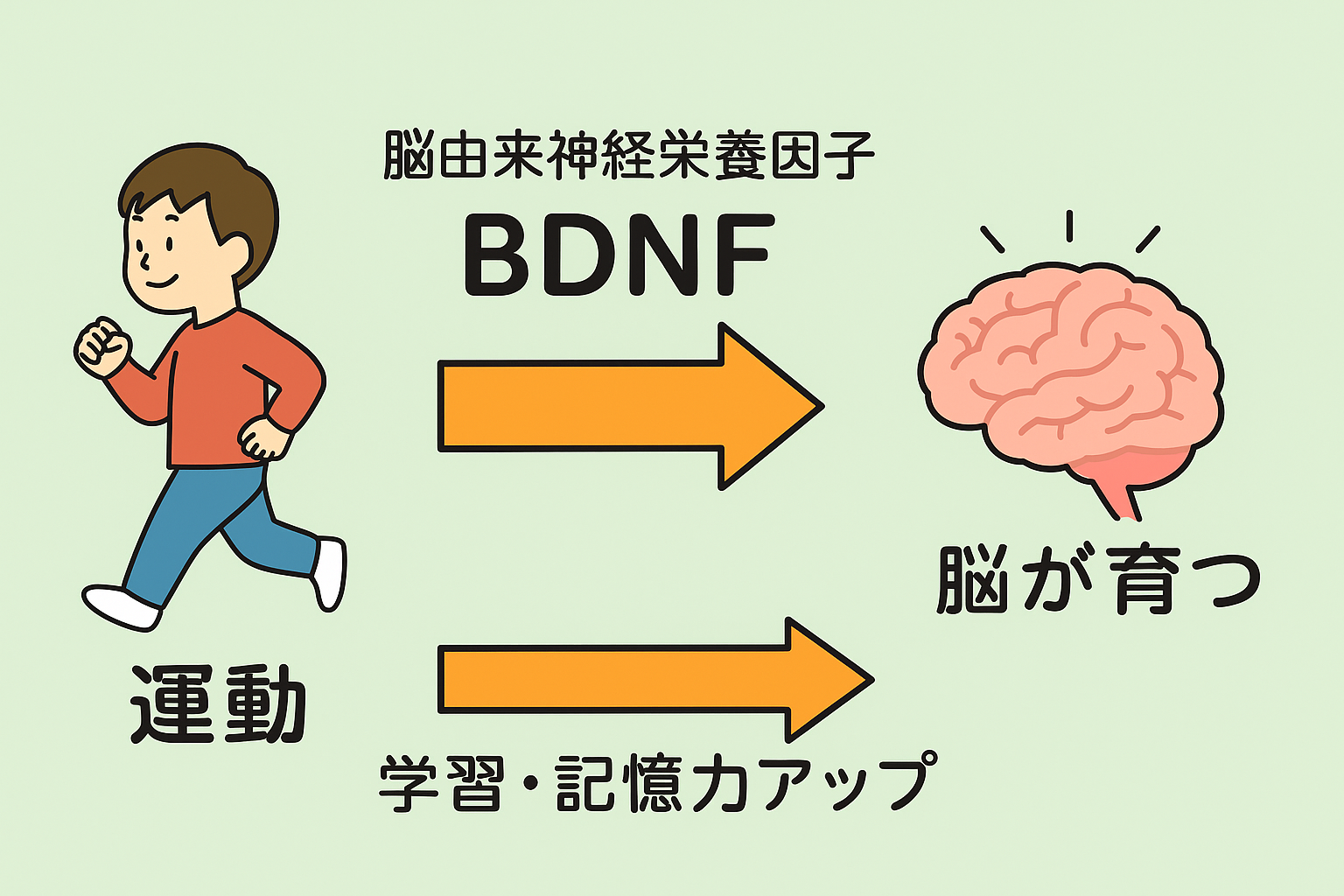

コメント