目をつぶっていても、自分の手がどこにあるか分かる。ペンを握ったとき、ちょうどいい力加減で文字を書ける。
これらはすべて「固有覚」という感覚のおかげです。
固有覚は、関節や筋肉にある受容器が、体の位置・動き・力加減を脳に伝える感覚で、姿勢保持や運動調整の基盤となります。
この記事では、固有覚が子どもの発達にどう関わるのか、どのように育てられるのか、不足や過敏があるとどうなるのかを、科学的根拠と発達支援の視点から解説します。
1. 固有覚とは?──体のGPSセンサー
固有覚は、筋肉・腱・関節に存在する感覚受容器(筋紡錘、ゴルジ腱器官、関節受容器など)から得られます。
- 筋紡錘:筋肉の長さや伸び具合を感知
- ゴルジ腱器官:筋肉の張力(力の強さ)を感知
- 関節受容器:関節の角度や動きを感知
これらの情報は脊髄や脳幹を経由して大脳皮質や小脳に送られ、姿勢制御・運動の精度・力加減を可能にします。
2. 固有覚が発達に果たす役割
① 姿勢保持
- 固有覚は、無意識に体の位置を把握し、バランスを崩さないように筋肉を微調整します。
- 座っているときに背中が崩れない、立っていても安定していられるのは固有覚のおかげです。
② 力加減の調整
- ペンで文字を書く、コップを持つ、ボールを投げる際の力加減は固有覚でコントロールされます。
- 固有覚が弱いと、字が薄すぎたり、逆に紙が破れるほど強く押してしまうことがあります。
③ 運動学習の効率化
- 固有覚は運動のフィードバックを脳に伝えるため、繰り返し動作の学習に不可欠です。
- 新しい動きを覚えるときや、スポーツでの動作精度の向上に役立ちます。
④ 情緒の安定
- 固有覚刺激は脳を落ち着かせる働きがあり、不安や多動傾向の軽減に寄与します。
- 重い毛布や加重ベストが落ち着きをもたらすのはこの作用によります。
3. 固有覚はどうやって育っていくのか?
乳児期(0〜1歳)
- 寝返り、ハイハイ、つかまり立ち
- 抱っこで上下に揺れる
- 手足を口に運ぶ
幼児期(1〜6歳)
- 全身を使った遊び(登る、押す、引く)
- お手伝い(荷物を持つ、椅子を運ぶ)
- ジャンプや片足立ち
学童期(6〜12歳)
- 鉄棒、うんてい、綱引き
- スポーツ(サッカー、バスケ、ラグビーなど)
- 筋力トレーニング(自重運動)
4. 固有覚が未発達・過敏・鈍麻だとどうなる?
未発達・弱い場合
- 姿勢が崩れやすく、授業中に体が揺れる
- 力加減が不適切(握力の調整が苦手)
- 不器用で運動スキルの習得に時間がかかる
- 粗大運動や微細運動の両方に影響
過敏な場合
- ちょっとした押し合いや接触でも不快
- 荷物を持つことを避ける
- スポーツや運動に消極的
鈍麻な場合
- 強い刺激(ジャンプ、押し合い)を求め続ける
- 授業中や食事中に体を動かし続ける
- 落ち着きがない印象を持たれやすい
5. 固有覚を育てる遊びと活動
① 押す・引く・持ち上げる
- 綱引き、相撲ごっこ
- 荷物運びのお手伝い
- バランスボールでの押し合い
② ぶら下がる・持ち上がる
- 鉄棒、うんてい
- ロープ登り
- 懸垂(補助あり)
③ 重さを感じる
- 水の入ったペットボトルを運ぶ
- 砂袋やメディシンボール遊び
- 加重ベストや重い毛布
④ 家庭でできる工夫
- 洗濯物を運ぶ
- 布団の上げ下ろし
- 掃除機や雑巾がけ
6. 科学的根拠
- 感覚統合理論によると、固有覚は前庭覚と統合されることで、より精度の高い姿勢制御と運動調整が可能になる。
- 研究では、固有感覚受容器からの情報がなければ、体の位置を正確に把握できず、運動がぎこちなくなることが示されている。
- 感覚統合訓練や筋力トレーニングは、固有覚の入力を増やすことで運動機能や集中力を改善できると報告されています。
まとめ
固有覚は、体の位置・動き・力加減を脳に伝える重要な感覚であり、学習や生活動作の土台です。
現代の子どもたちは、重いものを持つ・ぶら下がる・押し合うといった遊びが減っており、固有覚を鍛える機会も少なくなっています。
日常生活や遊びの中で意識的に固有覚を刺激することで、姿勢の安定・運動スキル・集中力の向上が期待できます。
すこっぴーラボでは、理学療法士が専門的な視点でお子さんの動きや特徴を丁寧に分析し、保護者の方や先生と一緒に最適なサポート方法を考えます。
「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします。


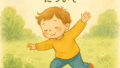
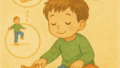
コメント