「うちの子、右手ばかり使う」「片足立ちが片方だけ苦手」「いつも同じ足で蹴っている」──
こうした左右差(側性)は、子どもの発達過程で自然に見られる現象です。
しかし、左右の使い方に極端な偏りがある場合、
・体幹バランスの乱れ
・姿勢の歪み
・運動協調の遅れ
につながることもあります。
本記事では、理学療法士の視点から、
「なぜ左右差が生まれるのか」「どうサポートすればよいか」
を科学的根拠に基づいてわかりやすく解説します。
1️⃣ 左右差はどうして生まれるの?
― 脳の発達と「利き手・利き足」の関係 ―
人間の脳は左右で役割が異なり、この「脳の側性化」が3〜6歳頃に明確になります。
この時期に「利き手」「利き足」が形成され、運動の得意・不得意が現れてきます。
🔍 最新研究から見た側性発達
- 利き手側は非利き手よりも運動制御が精密である¹⁾²⁾と報告。(一部の課題では差が見られないため、タスク依存)
- 発達性協調運動障害(DCD)の子どもは下肢の左右差が顕著³⁾⁴⁾であると報告。
- 足の利き(footedness)は脳の左右機能差やバランス能力と深く関連⁵⁾しているとされています。
つまり、「利き手・利き足」の発達は脳の成長と密接に関係しており、
その過程で生じる左右差が強すぎる場合、体の動きのバランスに影響を及ぼす可能性があるのです。
2️⃣ 左右差が強いときに見られるサイン
以下のようなサインが見られる場合は、左右差が発達のバランスに影響している可能性があります。
| 動作 | 左右差が強いときのサイン |
|---|---|
| 立つ・歩く | 片側に体重をかける、片足立ちでぐらつく |
| 階段昇降 | 毎回同じ足から上がる/下りる |
| ボール遊び | 片足だけで蹴る、反対側が不器用 |
| 手先の動き | 片手でしか作業しない、両手動作がぎこちない |
| 姿勢 | 立位・座位で体が傾く、骨盤の左右差が大きい |
こうした「動きの偏り」が続くと、
筋力・バランス感覚・協調性の発達に影響することがあります。
3️⃣ 理学療法士が見る「左右差評価」のポイント
理学療法士は、動作・筋肉・バランスを総合的に観察します。
✅ チェックポイント
- 利き手・利き足の定着度
→ どちらの手足を自然に選ぶか/使い分けができているか。 - 体幹と骨盤の左右差
→ 立位での重心の偏り、座位姿勢の傾き。 - 左右の下肢の筋力・可動域
→ 片足立ち、スクワット、ジャンプでの安定性。 - 交互運動・協調性
→ スキップ、縄跳び、ボールキャッチなど左右の切り替えの滑らかさ。
これらを観察することで、「どちらが使いやすいか」「どちらが苦手か」を明確にできます。
4️⃣ 左右差を整えるための支援と家庭でできる工夫
🏠 家庭でのサポート例(遊びながらバランスを整える)
| 目的 | 具体的な遊び・動作例 |
|---|---|
| 非利き側を使う | 反対の手で絵を描く、左足でボールを蹴る |
| バランス強化 | 片足立ちゲーム、平均台、クッションの上歩き |
| 協調性アップ | スキップ、左右交互ジャンプ、縄跳び |
| 体幹安定 | 四つ這い姿勢で左右の手足を交互に上げる(クロス運動) |
💡 ポイント
- 「苦手側」にも小さな成功体験を積ませる。
- 無理強いせず、遊びの中で自然に取り入れる。
- 音楽・リズムに合わせた運動は左右の協調を促進。
バランス練習やヨガのポーズなどで遊ぶのもおすすめです!
5️⃣ エビデンスに基づく運動支
非優位側を使うトレーニングが「運動制御能力の向上」に有効である⁶⁾ことも確認されています。
👉つまり、「苦手側を使う」「交互運動を取り入れる」ことがとても大切。
6️⃣ 保護者へのアドバイス
- 左右差は「矯正」するよりも「バランスよく使う」ことが大切
- 日常生活の中に、反対側を使う遊びを取り入れる
- 強い左右差や姿勢の歪みが気になる場合は、理学療法士や作業療法士に相談を
左右差は「伸びしろ」でもあります。
使いにくい側を少しずつ育てることで、運動能力全体の底上げにつながります。
🔚 まとめ
- 左右差は発達の自然な過程だが、強すぎる場合はサポートが必要
- 脳の側性発達と運動バランスには密接な関係がある
- 非利き側を使う遊びや交互運動で、バランスと協調性を整える
- 運動療育(Motor-based Intervention)は科学的に有効
すこっぴーラボでは、理学療法士の視点をもとに、
子どもの発達・姿勢・運動バランスに関する支援や情報発信を行っています。
左右差・バランスに関する無料相談も受け付けていますので、
気になることがあればお気軽にご連絡ください。


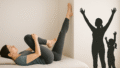

コメント