「落ち着きがない」「すぐに気が散る」「授業に集中できない」――こうした困りごとを持つ子どもたちに対して、つい「行動を直さなきゃ」と思ってしまいがちです。
しかし実際には、多くのケースで「子ども自身の問題」ではなく、「環境から受ける刺激の多さや合わなさ」が背景にあります。
つまり、子どもの行動を変える前に、まず“環境を整える”ことが効果的で優しい支援になるのです。
参考になる本はこちら👇
※本記事は医療的診断を行うものではありません。ADHDやASDの正式な診断は医師にご相談ください。ここでは、ご家庭や学校で役立つ工夫や考え方の一例を紹介しています。
1. 環境調整が必要になる背景
感覚過敏・感覚統合の課題
ASD(自閉スペクトラム症)やADHDの子どもには、聴覚・視覚・触覚などへの「過敏さ」や「鈍感さ」がよく見られます。
- 蛍光灯のちらつきが気になる
- 服のタグや布団の素材が不快
- 周囲の小さな音に反応してしまう
これらは本人にとって強いストレスであり、学習や生活のパフォーマンスを大きく下げる要因となります。
注意のコントロールの難しさ
ADHDの子どもは、周囲の刺激にすぐ注意を奪われやすい傾向があります。教室のざわめきや家庭でのテレビの音、机の上の物の多さ…これらがすべて集中の妨げとなります。
2. 教室でできる環境調整の工夫
(1) 座席の工夫
- 前列や壁際に座らせる
→ 周囲の視覚的な刺激を減らし、集中を助ける。 - ドアや廊下側を避ける
→ 出入りの音や動きで注意が散りやすいため。 - クッションやバランスシートを使用
→ 体幹が不安定な子の座位保持を助け、姿勢の崩れを防ぐ。
(2) 照明の工夫
- 蛍光灯のちらつきや眩しさを避ける
- 自然光を取り入れ、カーテンで調整する
- タスクライトで机上をピンポイントに照らす
照明の質は、特に視覚過敏の子にとって重要です。強い光が「頭痛」「目の疲れ」「不安感」を引き起こすことがあります。
(3) 音の工夫
- イヤーマフ・ノイズキャンセリングヘッドホンの活用
- カーペットやカーテンで反響を減らす
- 教師の指示は「短く・わかりやすく・視覚的に補助」
聴覚情報処理が苦手な子どもには、口頭の説明+板書やカードといった二重の提示が有効です。
3. 家庭でできる環境調整の工夫
(1) 学習スペース
- 机の周囲はシンプルに
- パーテーションで仕切りを作る
- 決まった場所で学習する
「どこでやるか」を一定にすると、脳が「ここは学習する場所」と認識しやすくなります。
(2) 音とリズム
- 静かなBGMやホワイトノイズで外音を均質化
- タイマーを使い、学習と休憩のリズムをつくる
ADHD傾向の子には、「あと◯分で終わる」が視覚的に見えると安心感につながります。
(3) 生活環境
- ラベルや写真で「片付けの場所」を明示
- チクチクしない服、重みのある布団などで触覚に配慮
触覚は安心感と深くつながる感覚です。加重毛布や好きな素材の毛布は、睡眠の安定にも効果があります。
4. OT/PT的な支援アイディア
理学療法士や作業療法士が取り入れる「感覚統合」の視点を活かすと、さらに効果的な環境調整ができます。
- 動きと静けさの切り替えを意識
授業前にジャンプやストレッチ → 学習、と流れを習慣化する。 - 体幹や前庭覚への刺激をプラス
バランスボール、スイング、ストレッチなどで落ち着きや集中力を促す。 - 視覚的支援(構造化)
スケジュール表、ToDoリスト、やることカードで「見通し」を持たせる。
まとめ
子どもたちの「行動」を変えるよりも、「環境」を整えることが、子どもに優しく持続可能な支援につながります。
- 座席・照明・音など、教室での工夫
- 学習スペース・音環境・触覚への配慮など、家庭での工夫
- OT/PT的な感覚統合の視点を取り入れたサポート
これらを組み合わせることで、子どもは「安心して学びに向かえる環境」を手に入れることができます。
すこっぴ―ラボでは、無料相談も受け付けていますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
「動作分析をしてみてほしい」「プロの目でアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
LINEやオンライン面談で、お子さんの困りごとやご不安を一緒に整理しながら、サポートの第一歩をお手伝いします。


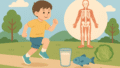

コメント