寒い季節になると、子どもの体調や行動にちょっとした変化を感じませんか?
「朝なかなか起きられない」「外で遊びたがらない」「なんだか姿勢が悪くなった」——そんな冬ならではの“子どもの変化”には、実は身体的な理由があるのです。
本記事では、理学療法士の視点から、寒い季節に起こりやすい子どもの身体・体調の変化をわかりやすく整理し、家庭や学校で実践できるケア方法を紹介します。
❄️ なぜ寒くなると子どもの体が変わるの?
冬の冷えは、子どもの身体にさまざまな影響を与えます。主な変化は次の3つです。
- 筋肉がこわばりやすくなる(冷えによる血流低下)
- 運動量が減り、姿勢を支える筋力が低下する
- 自律神経が乱れやすく、体調を崩しやすくなる
これらの変化は、大人より体温調節機能が未熟な子どもにとって、特に影響が出やすい点です。
🧍♀️1.寒さで筋肉がこわばり、動きがぎこちなくなる
寒くなると、私たちの身体は自然に肩をすくめたり背中を丸めたりして、熱を逃がさないようにします。
これは体温を保つための正常な反応ですが、同時に筋肉が縮こまり、関節の動きや筋の反応が鈍くなる原因にもなります。
子どもも同じように、寒い時期は体を動かしづらく感じることが多いのです。
この「動きにくさ」は、気分や意志の問題ではなく、筋肉の温度(筋温)の低下による生理的な現象であることが分かっています。
成人を対象とした複数の研究では、
筋温が1℃下がるとおおむね3〜5%の筋力低下が生じることが示されています¹⁾。
また、体温・筋温の低下が筋力とパワー出力を3〜14%低下させることも確認されており、
筋温の低下が筋力変動の主要な要因であることが裏付けられています。
なお、小学生などの子どもを対象とした直接的な研究は現時点でありません。
しかし、子どもは大人より筋量が少なく皮下脂肪も薄いため、冷えによる筋温低下の影響を受けやすいと考えられています。
つまり、「寒くて動きたくない」は、身体が“動きにくい状態”になっているサインでもあるのです。
🔹家庭でできる工夫
- 朝の支度前に10秒の“手足ぶらぶら体操”や深呼吸を
→ 血流を促すだけでも筋肉が温まり、動きやすさが変わります。 - 室内でも音楽に合わせて動く時間をつくる
→ 踊る・ジャンプするなど“楽しく動く”ことで、自然に筋温を上げられます。 - 座りっぱなしを防ぐ
→ 暖房の効いた室内でも、30分に1回立ち上がるだけで代謝を維持できます。
💡ポイント:
「ウォームアップ=スポーツの前だけ」と考えず、朝の生活習慣にも“身体を温めるひと工夫”を。
それが冬のだるさ・動きづらさを防ぐ第一歩です。
朝のストレッチや軽い運動を取り入れても、冷えやすい手足が温まりにくいこともあります。
そんなときは、手袋やネックウォーマーなどで“冷えやすい末端を守る”工夫もおすすめです。
とくに、手首・首・足首は「三首」と呼ばれ、体温を逃がしやすいポイント。
この部分を温めることで、全身の血流も良くなりやすいとされています。
🏃♂️2.外遊びが減ると筋力・姿勢バランスが低下する
冬になると寒さや天候の影響で、子どもの外遊びが減りやすくなります。
しかし、この「活動量の低下」が、筋力や姿勢の発達に影響することが分かっています。
👦 子どもへの影響
小学生を対象とした直接的な研究はまだ少ないものの、
冬に外遊びが減ると、体幹や下半身にかかる刺激が少なくなることは明らかです。
その結果、筋力・バランス力・姿勢の安定性が低下し、疲れやすくなったり集中しづらくなったりすることがあります。
🔹家庭・学校でできる対策
- 30分に1回、立ち上がって肩回し・前屈・ジャンプなどを習慣化。
- 椅子の高さを見直し、足裏がしっかり床につく姿勢をつくる。
- 「寒いけど少しだけ外に出よう!」と、短時間の散歩を習慣に。
💡ポイント:短時間でも体幹を使う動き(縄跳び・坂道歩き・雑巾がけ)は、姿勢維持にとても効果的です。
🌡️3.冷えが自律神経に影響し、体調を崩しやすくなる
自律神経は、体温・血圧・睡眠リズムなどを調整しています。
寒暖差が激しくなると、このバランスが崩れ、だるさ・頭痛・腹痛・食欲低下・不眠などが起こることがあります。
研究でも、寒冷刺激が交感神経を活性化させ、血管収縮や心拍変化をもたらすことが報告されています²⁾。
つまり、「冬になると体調を崩しやすい」は、生理的な反応でもあるのです。
🔹自律神経を整える習慣
- 朝日を浴びる → 体内時計をリセットし、夜の寝つきが良くなる。
- 朝食で身体を温める → 味噌汁・スープ・白湯などで内側から代謝を上げる。
- 寝室の温度は18〜20℃、湿度は50〜60%が理想。
- 日中に軽く体を動かす → 軽い運動が副交感神経の働きを助け、ストレス耐性を上げる。
自律神経に関してはこちらの記事もおすすめです👇
感情のコントロールが苦手な子への運動的アプローチ | すこっぴ―ラボ
😴4.睡眠リズムの乱れに注意
冬は日照時間が短くなるため、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌リズムがずれやすくなります。
研究によると、光量が減ることでメラトニンの分泌タイミングが遅れ、寝つきや睡眠の深さに影響することが確認されています³⁾⁴⁾。
🔹家庭での工夫
- 朝起きたらすぐカーテンを開けて自然光を浴びる。
- 夜はスマホ・タブレットを早めにオフ。ブルーライトはメラトニンを抑制します。
- 寝る前にストレッチや深呼吸で身体を温め、入眠しやすくする。
💡寝る直前の「温かい飲み物(白湯やハーブティー、ココア)」も効果的です。
💬5.冬に見られる“心の変化”にも寄り添って
寒さや活動量の低下は、子どもの気分や意欲にも影響します。
実際、日照時間の減少が気分の落ち込み(いわゆる「季節性情動変化」)と関係していることが知られています。
「最近なんとなく元気がない」「遊びに誘っても乗り気じゃない」
そんなサインが見えたら、身体的な疲労だけでなく、心のバランスの変化も考えてあげましょう。
🔹親・先生にできること
- 「寒いから動きにくいよね」と共感の声かけをする。
- 無理に運動を強いるより、“一緒に”体を動かす姿勢を見せる。
- できたことを小さく褒めることで自己効力感を高める。
✅まとめ:冬こそ「小さく動いて温める」がキーワード!
寒さで体を守ろうとする反応そのものが、筋肉のこわばりや体調不良の原因になります。
だからこそ、冬こそ“少し動く・温める・整える”が大切です。
| 冬のよくある変化 | 対応のポイント |
|---|---|
| 筋肉のこわばり | 朝ストレッチ・軽い運動 |
| 運動不足・姿勢の崩れ | 室内でも定期的に動く |
| 自律神経の乱れ | 光・温かい朝食・リズムを整える |
| 睡眠の質の低下 | 光・温度・デジタル制限 |
| やる気の低下 | 共感+一緒に体を動かす |
小さな工夫が、子どもの体も心も元気にしてくれます。
家庭や学校で、日常の中に「体を温める・動かす」時間を取り入れてみましょう。
すこっぴーラボでは、理学療法士の視点から、子どもの発達や成長をサポートする情報を発信しています。
「冬になると体調を崩しやすい」「姿勢や運動のことを相談したい」などのお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
無料相談も受け付けております。
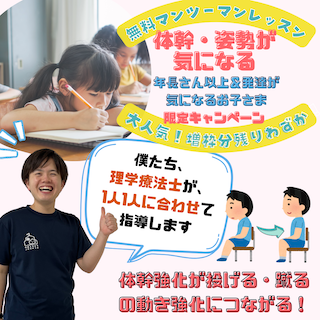



コメント