「説明してもなかなか伝わらない」
「見せたらすぐできた!」
「話を聞くより、体を動かすと理解が進む」
こんな経験はありませんか?
実はそれ、感覚優位性(dominant sense)の違いが関係しているかもしれません。
人は誰でも、情報を「目」「耳」「体」など、使いやすい感覚チャンネルを通して受け取っています。
前回の記事では、感覚優位性とは「どの感覚を主に使って世界を理解しているか」という個性であるとお伝えしました。
今回はその中でも特に大切な、視覚・聴覚・体感覚の3つのタイプ別に、理解の仕方と支援の工夫を紹介します。
1. 視覚優位(Visual Type)──「見てわかる」タイプ
🔹 特徴
- 話を聞くより、見た方が理解が早い
- 絵・図・写真・文字情報が得意
- 手順やルールを“見える化”すると落ち着く
- 口頭での説明だけだと混乱することがある
視覚優位の子は、視覚情報で整理・記憶する力が高いタイプです。
言葉で長く説明するより、見本や図を使う方がスッと理解できます。
🔹 家庭・授業での工夫
| 場面 | 支援の工夫 |
|---|---|
| 支度や準備 | 手順カードや写真を貼る。「①着替え → ②歯みがき → ③荷物チェック」などを図示 |
| 学習 | 板書やノートに色分け、イラストを使って整理。文字だけでなく「視覚で区別」できる工夫を |
| 指示やルール | ピクトグラム・ポスター・スケジュール表などで見える形にする |
| 新しい動作の習得 | 実際に見本を見せてから説明する。ジェスチャーや実物を併用すると効果的 |
🔹 伝え方のポイント
- 「こうしてね」より「これを見てね」
- 話すときは目線を合わせて、ジェスチャーで補助
- 注意やお願いも「見える形」で残す(紙・カードなど)
👉 “見える手がかり”を増やすことで、理解と安心がぐっと深まります。
2. 聴覚優位(Auditory Type)──「聞いてわかる」タイプ
🔹 特徴
- 話の内容をすぐ理解できる
- 音やリズムで覚えるのが得意
- 周囲の声や音に敏感なことがある
- 同時に複数の人が話すと混乱しやすい
聴覚優位の子は、耳からの情報処理が得意です。
口頭での説明や会話を通じて理解を深め、音の抑揚やリズムを手がかりに記憶する傾向があります。
🔹 家庭・授業での工夫
| 場面 | 支援の工夫 |
|---|---|
| 指示を出すとき | 一度にたくさん話さず、短く区切って伝える。「まず〇〇してね」「終わったら△△しよう」など順番を意識 |
| 学習 | 音読・歌・リズムを取り入れる。言葉で説明を補足すると理解しやすい |
| 集中が切れやすいとき | 周囲の音(テレビ・会話)を減らして、落ち着ける環境にする |
| 記憶のサポート | 声に出して確認、リズムで覚える、クイズ形式にする |
🔹 伝え方のポイント
- 明るい声・一定のトーンで安心感を
- 重要な言葉はゆっくり・繰り返す
- 同時に話さず、一人ずつ・一つずつ伝える
👉 聴覚優位の子には、「耳で安心できる環境」が学びの基盤になります。
3. 体感覚優位(Kinesthetic Type)──「動いてわかる」タイプ
🔹 特徴
- 体を動かしながら学ぶと理解が深まる
- じっと聞く・見るだけの学習は苦手
- 手を動かしたり、体を使って試すのが好き
- 動きながら考えることで集中しやすい
体感覚優位の子は、「体で感じること」を通して情報を整理します。
言葉や図だけでなく、実際に“やってみる”ことで理解が進むタイプです。
🔹 家庭・授業での工夫
| 場面 | 支援の工夫 |
|---|---|
| 学習 | 積み木・ブロック・カードなど、手を使って理解できる教材を使う |
| 新しい概念の学び | 実際に体を動かして体験する(例:算数なら物を並べて数える) |
| 長時間の学習 | こまめに動く休憩を入れる。「伸びをする」「ジャンプを3回」など短時間でOK |
| 遊びや療育 | 体を使う遊びを通して言葉やルールを学ぶ(例:色鬼・リズム遊びなど) |
🔹 伝え方のポイント
- 「やってみよう」「一緒に動いてみよう」と体験に誘う
- 触覚・重さ・バランスなどを感じられるように工夫する
- 正解を言葉で教えるより、「感じて理解する」時間を大切にする
👉 体を使うことそのものが“学び”になります。
動きの中で理解が深まり、自信が育ちます。
4. どのタイプにも共通すること
実際の子どもたちは、どれか1つだけが優位というより、
複数の感覚を組み合わせて使っていることが多いです。
たとえば、
- 見て理解しながら、声に出して覚える(視覚+聴覚)
- 聞いたことを動きで確認する(聴覚+体感覚)
このように、感覚をつなげて使う力(感覚統合)が発達していくことで、
学びや行動がよりスムーズになります。
5. 「伝え方を変える」と、子どもは変わる
子どもがうまく理解できないとき、
「集中していない」「やる気がない」と感じてしまうことがあります。
でも、それは「情報の入り口」が合っていないだけかもしれません。
大人が伝え方を少し工夫するだけで、
子どもの表情がパッと明るくなる瞬間があります。
それは、
「この方法ならわかる!」という安心感を得たときです。
その積み重ねが、
“できる力”を育て、自己肯定感を支えていきます。
■ まとめ
- 感覚優位性とは、「情報をどう受け取るのが得意か」という脳の個性
- 視覚優位:見える手がかりを活かす
- 聴覚優位:言葉・リズム・声かけを工夫する
- 体感覚優位:動いて体験する中で理解を深める
- 子どもによって得意な感覚の組み合わせは異なる
伝え方を変えれば、子どもの理解も変わる。
それが、感覚の特性を活かした支援の第一歩です。
すこっぴーラボでは、理学療法士の視点から、
子どもの発達や感覚特性に合わせた支援・学び方の工夫を発信しています。
「うちの子はどんな感覚が得意なんだろう?」
「家庭や学校での伝え方を工夫したい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
無料相談も受け付けております。
公式LINEも是非👇



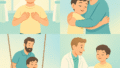
コメント