 学校
学校 運動が苦手でも大丈夫!子どもの発達を促す理学療法士直伝の遊び
運動が苦手な子どもの発達を支える方法を理学療法士が解説。家庭でできる遊びや成功体験の積み重ね方を紹介し、「できない」を「できた!」に変えるサポートのコツを伝えます。
 学校
学校  発達
発達 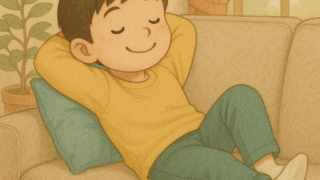 不適合
不適合  感覚
感覚 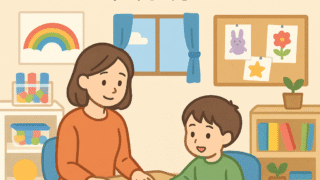 学校
学校  学校
学校  発達
発達 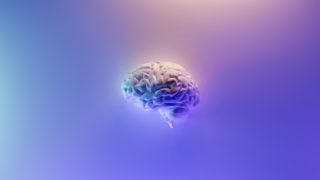 発達
発達