 学校
学校 【理学療法士が解説】冬休み明けに小学生がしんどくなる理由とは?
冬休み明けに小学生が朝起きられない、学校を嫌がる、疲れやすいのはなぜ?休み明けは生活リズムの乱れにより、混乱してしまう子も多いです。発達が気になる子に起こりやすい変化と、家庭でできる対処法を理学療法士の視点から解説します。
 学校
学校  グレーソーン
グレーソーン  学校
学校  学校
学校 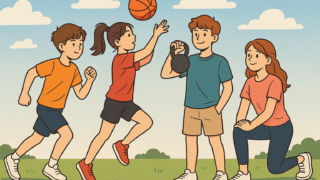 学校
学校  不適合
不適合 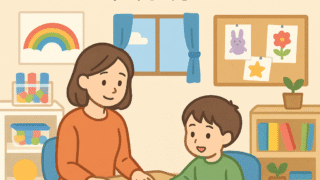 学校
学校 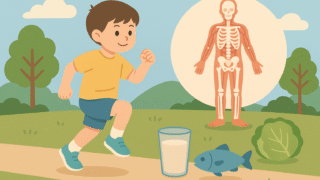 姿勢
姿勢  学校
学校  学校
学校